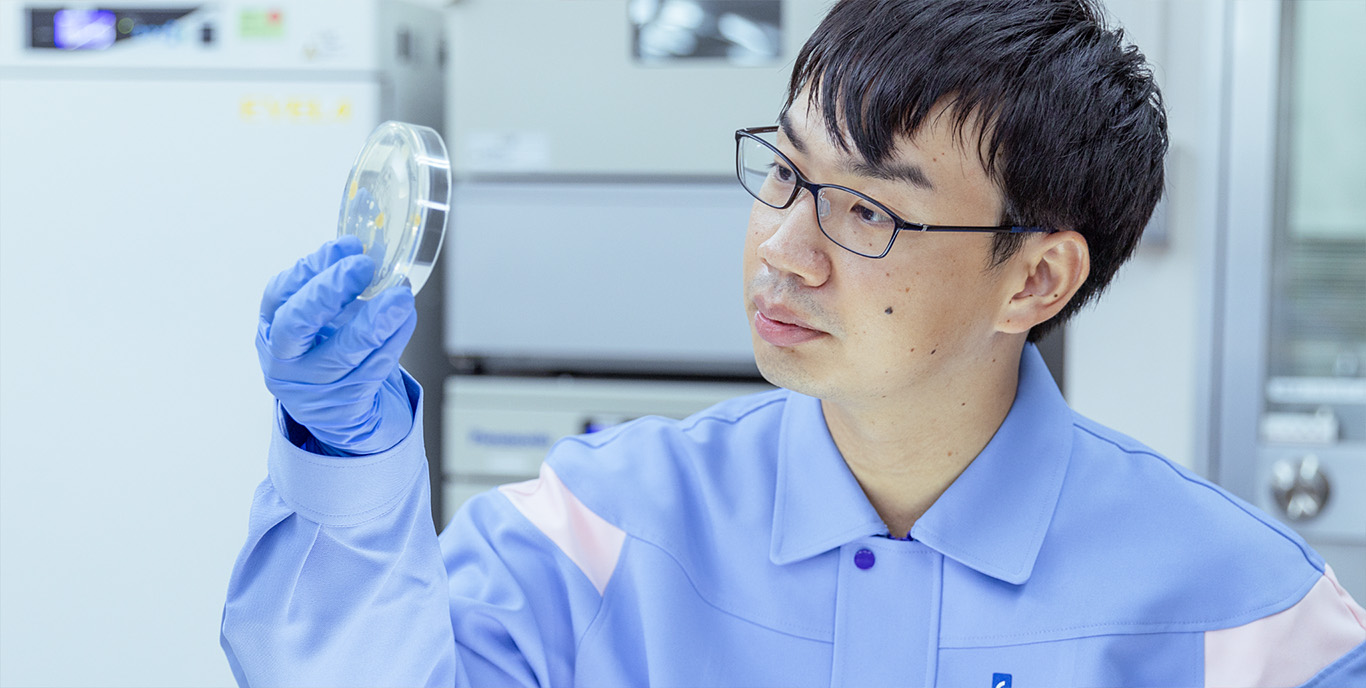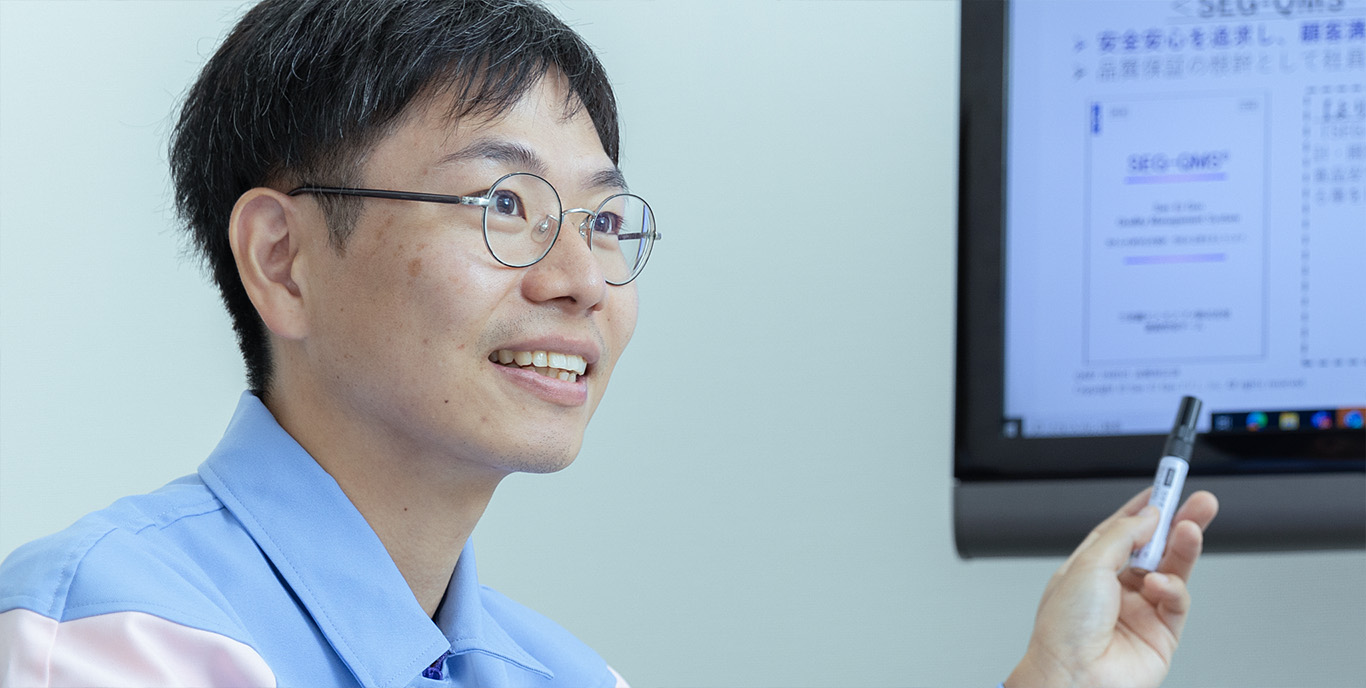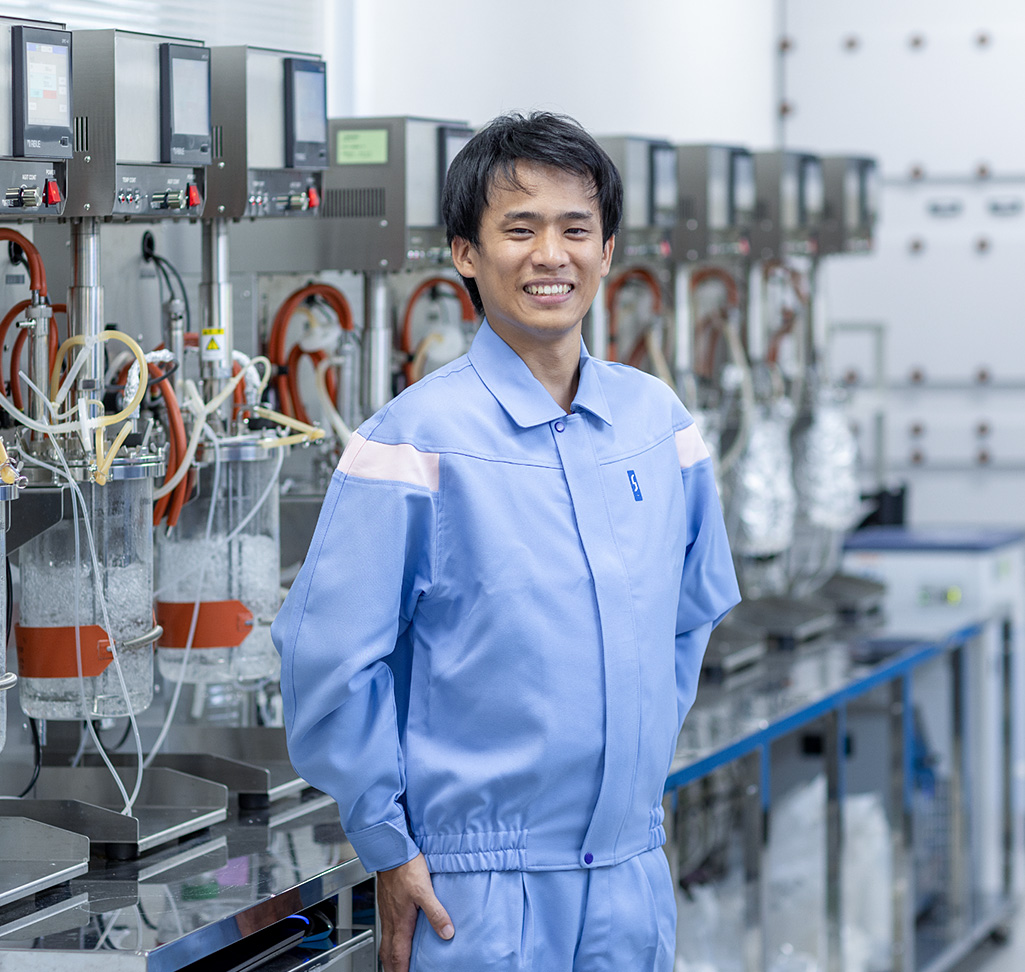
持続可能な「バイオものづくり」で
未来の社会を支える
- 研究部門
- K.T.
農学部 応用生命化学科
2019年入社
事業本部 発酵技術研究所
プロフィール
お酒好きが高じて発酵食品に興味を持ち、学生時代には微生物の培養と遺伝子機能の解析を学ぶ。この時に得た知識が、現在の発酵技術研究所での業務に直結している。休日にはアウトドアに出かけたり、オンラインゲームや電子ピアノを楽しんだりと多趣味。
小さなフラスコから量産へ
実験が実を結ぶ瞬間
入社以来、長い歴史で培った知識と経験を活かしながらも、それに固執せず最新技術を追求し続ける当社の社風を肌で感じてきました。私が携わる「バイオものづくり」も、そんな社風で磨き上げてきた技術の一つ。微生物培養の技術を用いることにより、低コストかつ効率的に生産できる食品素材を開発することが研究テーマで、持続可能な社会の実現という観点からも近年注目を集めています。この業務を通じて、未来の社会を支える技術が身についていると実感します。
研究所では、フラスコでの検討や実機製造を見据えたスケールアップ試験を繰り返す毎日です。その集大成となるのが、実機製造への立ち会い。特に初めての立ち会いは印象的でした。日中に結果が出ず、帰宅後も成功を祈りながら、ほとんど眠れず朝を迎えたことを覚えています。結果的に一度目は思った通りの結果が得られなかったものの、ラボで再検討した後、2度目の製造で軌道にのせることができました。何度も検討を重ね、量産化への道が拓けた瞬間は感慨深いです。

「失敗すらも楽しい」
そう思えるほど没頭できる仕事
1年目は実験の結果ばかりを追求してひたすら手を動かしていましたが、3年目に後輩指導が始まると、自分の知識と経験不足が仇となり多忙を極めました。仕事の優先順位と時間配分を意識し始めたのはこの頃からです。資料作成などのすべての業務において「スピード」と「質」のバランスにこだわって仕事に臨むようになり、今はようやく自分が一段階成長したことを実感しています。
この6年間の研究開発は試行錯誤の連続でしたが、それでも、実験が好きな気持ちが揺らいだことはありません。思い通りの実験結果が得られなくてもめげずに考察し、持てる知識を総動員して何度もトライする、その過程すら楽しんでいます。研究には失敗がつきものだからこそ、成功した時の達成感が大きいです。これまで商品開発に携わってきたさまざまなメーカーの食品や飲料が店頭に並んでいるのを見かけるたび、研究者としての誇りを感じます。

ひらめいた実験をすぐにできる
研究者にとって恵まれた環境
私が入社を決めた最大の理由は、大阪の中心部にある本社にさまざまな食品添加物や食品素材を担当する複数のユニットが集結し、各分野の専門家と意見を交わしながら協力して研究開発を進められることでした。加えて、工場が同じ敷地内に併設されているため、必要に応じて製造担当者とコミュニケーションをとり、常に生産も意識した研究ができます。また機器が充実しているため、ふと思いついた実験をすぐに試すこともでき、研究者にとってこのうえなく恵まれた環境だと感じます。
今後、当社が世界から必要とされる企業になるためには、持続可能な社会の実現に向けて、独自の視点で製品開発を進めていくことが重要です。私も「バイオものづくり」の専門家として多くの製品開発に携わり、身につけた知識と技術を社会の未来に還元していきます。大学との共同研究や学会での情報収集にも励み、社内外の多くの方とのコミュニケーションを大切に、自分の知見に偏らない謙虚な研究者であり続けたいと思います。
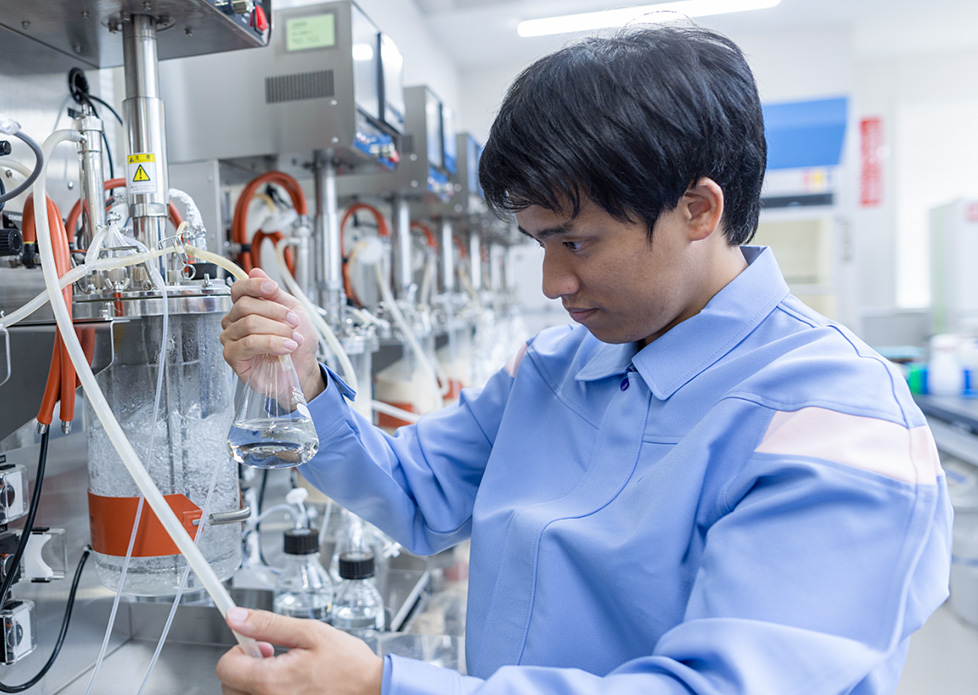
ともに「食の未来」を開拓できる
あなたとの出会いを
心から楽しみにしています。


 新卒採用サイト
新卒採用サイト
 新卒採用サイト
新卒採用サイト